誠に勝手ながら、鎌倉倶楽部茶寮西鎌倉店は、
閉店することとなりました。
約5年間という短い間 でしたが、お茶を通して、
たくさんの暖かいお客様に出会えたこと、
深く感謝いたします。
開店以来のご愛顧誠にありがとうございました。
尚、鎌倉倶楽部茶寮小町店は現在営業致しております。
鎌倉駅から徒歩2分程の立地にございます。
皆々様がお茶でほっと一息~お寛ぎいただけますように、
スタッフ一同心よりお待ち致しております。
引き続き鎌倉倶楽部茶寮を宜しくお願い致します。
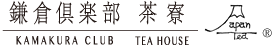
誠に勝手ながら、鎌倉倶楽部茶寮西鎌倉店は、
閉店することとなりました。
約5年間という短い間 でしたが、お茶を通して、
たくさんの暖かいお客様に出会えたこと、
深く感謝いたします。
開店以来のご愛顧誠にありがとうございました。
尚、鎌倉倶楽部茶寮小町店は現在営業致しております。
鎌倉駅から徒歩2分程の立地にございます。
皆々様がお茶でほっと一息~お寛ぎいただけますように、
スタッフ一同心よりお待ち致しております。
引き続き鎌倉倶楽部茶寮を宜しくお願い致します。